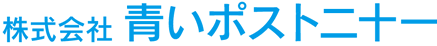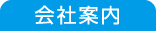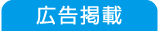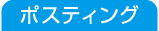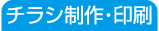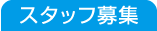原発による環境及び人的影響⑦
チェルノブイリ原発事故の原因真相
危険で軟弱な地盤の上に設置された大型原子炉が今もなお運転中
(前号より)
先ず、世界で最初の商業用原子力発電所を運転開始したのはソ連だった(1954年6月、オブニンスク発電所5000kw)。
ソ連が商業用原子炉を開発しているというニュースは米国に衝撃を与えた。それはすぐに米国のアイゼンハワー大統領の「原子力平和利用に関する声明」へと発展した。
その声明に対し、すぐに反応したのが中曽根康弘衆議院議員だった。
原子力研究のために予算の修正案を出して2億6000万円の予算の上積みを可決させた。
そして、1956年(昭和31年)1月1日に原子力を推進するための原子力委員会が設立した。初代委員長の故正力松太郎氏は実用段階に入っている英国のコールダーホール(ガス冷却式)型原発を急いで導入しようとしていた。
そして、1957年(昭和32年)に日本原子力発電(株)が設立され、耐震用に改良された英国製の「コールダーホール改良型」が発注された。しかしながら、耐震のために炉心を大きくしたり、緊急停止装置を付けたりで結局は建設費が大きく膨らみ、石油火力よりも発電コストが高くなってしまった。
そこへ、原子力潜水艦に使われた軍事用原子炉を急遽大型化して商業用としたGE製の「軽水炉」が日本の電力会社にセールスをかけてきた。その結果、東京電力が最初のGE製の沸騰型軽水炉を福島県に導入した。それが今回の大事故を起こした福島第一原子力発電所1号機と言う訳である。
そして、それと同じGE製の沸騰水型の軽水炉が2009年1月に廃炉となった浜岡原発1号機と2号機なのである。
廃炉が決まった、その年の8月11日午前5時7分に、静岡県御前崎沖の駿河湾を震源とするM6・5、震度6弱の地震が起きた。(静岡沖地震)
幸い最も危険な2号機はすでに廃炉、4号機は点検のため運転停止中だった。残る3号機と5号機は自動停止したが5号機の地盤は軟弱で揺れが増幅して震度7相当の揺れになってしまった為に、冷却装置がうまく働かず制御棒が損傷するというほどの事故を起こした。
この事からも、もし1号機・2号機が廃炉でなく運転していたら福島原発の様に大きな原子炉事故となっていたであろう。そうなると、東京・名古屋を含む関東・中部圏は放射能の雨にみまわれ居住不可能となる位の大惨事となった。
あるいは、この地震が今回の三陸沖と同じ強さだったら間違いなく浜岡原発は次々と原子炉が崩壊していたであろう。しかも、この5号機は出力が138万kwとチェルノブイリ原発4号炉や福島原発の各原子炉よりもはるかに大きいから、この原子炉1つの爆発で東京や名古屋圏はそれこそ放射性物質で全滅になっていたはずである。
そんな危険な軟弱な地盤の上に大型原子炉が4号機と共に今もなお運転中なのだから日本の原子力行政の恐ろしさの程がわかるであろう。
しかし、震度5で幸いに福島原発のときよりも地震が小さく、しかもこの5号機は最新式の沸騰水型原子炉(ABWR)で非常用炉心冷却装置(ECCS)の一環として原子炉隔離時冷却系(RCIC)が装備されており、電力喪失時でも原子炉から発生する蒸気でタービンを回して冷却水循環が行える装置がついていた。
余談だが、25年前に起きたチェルノブイリ原発事故は、このRCICに関する基礎実験中に起きたと言える事故なのである。
すなわち、原子力発電はウラン235という放射性物質に中性子をぶつけて核分裂を起こさせ、その核分裂から生じる熱の水蒸気の力でタービンを回し発電する仕組みだ。ところが、ウラン235の核分裂を止めるために制御棒を入れて原子炉を休止させても、原子炉の中では崩壊熱がまだ続いている。
崩壊熱とはウラン235が核分裂した後に生成された様々な放射性物質が壊変しながら出す熱のことである。
崩壊熱の量はウラン235が核分裂する時に出る熱の7%位から時間と共に1%以下に下がるが、それでも大きい熱であるから冷却しないと崩壊熱だけで燃料棒が溶けてしまう。燃料棒が溶けてしまった状態のことを炉心溶融と言い、メルトダウンとも言う。
そこで、今回の福島原発事故のように原発の全電源が喪失した場合、原子炉から出る崩壊熱を利用して発電し、その電力で発電所の設備を維持して原子炉を冷却するという実験をチェルノブイリ4号炉で行っていた時に誤って事故を起こしてしまったのではないかと私は考えている。
と言うのも、事故の真相というのは秘密のベールの中に隠されてしまっているから本当は良くわかっていない。一説では、タービンに送っている蒸気を止めて重量の大きいタービンの回転慣性力だけでどれ位多くの電力が作り出せるかを調べる実験と言われている。
チェルノブイリ事故は制限値を超えて手動で制御棒が抜かれていた
この実験だと全電源喪失とタービンへの蒸気配管が破断した場合の想定に対する実験ということになるが、このような実験は始めから作り出せる電力がわずかであることが計算上でも明らかなため、わざわざ稼働している原子力発電で実験を行うとは思えないし、それに危険すぎる。チェルノブイリ原子炉事故に至る複雑な実験過程を考えると、RCIC装置のための予備実験と考えたほうがつじつまが合いやすい。
そこで、余熱による電力供給の実験は先ず原子炉の出力を落とし、そこから崩壊熱だけによる蒸気発生でタービンを回して得られる電力でどれだけ発電所を維持できるかというデータ取りから始めていくことになるだろう。
さらに、制御棒を徐々に上げることによってどの出力地点でどれだけの発電所設備の電力がまかなえるかの実験を行おうとしていたのではないだろうか?
ところが、彼等はその時、キセノン(ゼノン)の毒効果(Poisoning effect)というのを知らなかった。簡単に説明すれば、原子炉の中の燃料であるウラン235が核分裂する時、5・6%の割合でテルル135が生成する。
テルル135は半減期が約30秒でヨウ素135に変わる。ヨウ素135は半減期6、7時間でキセノン135に変わるのである。
そして、問題なのは、このキセノン135が中性子を吸収して他の同位元素に変わることである。簡単に書くと、テルル135( 半減期約30秒)→ヨウ素135(半減期6、7時間)→キセノン135。
そこで原子炉が一定出力で動いている場合はテルル135からキセノン135に変わる量は常に一定であるし、キセノン135が中性子を吸収して消滅していく量も一定であるからバランスが保たれている。
ところが、原子炉を停止したり、出力が落ちたりすると、ウランの核分裂による中性子の発生が減るのでキセノン135が消滅しないで原子炉の中に蓄積されていく。このキセノンの蓄積量が最大になるのは原子炉停止後約12時間前後と計算されている。
そこで、12時間後に制御棒を抜いて原子炉を再起動しようとしても、キセノン135が中性子を吸収してしまうので、核の連鎖反応、つまり核の臨界にまで達しないで原子炉は動かない。これが原子炉をいったん停止させてしまうとしばらくは原子炉を休止する理由なのだ。当時ソ連は電力不足が逼迫していて原子炉を止めることをしなかった。だから、運転員達は原子炉を止めた後のキセノンの毒効果を知らなかったと言うよりも経験がなかったのかもしれない。
それゆえ、原子炉の出力を停止状態近くまで下げた後に起こったキセノンの毒効果を知らずに、運転員達が原子炉の出力を上げるために制御棒を抜くが、出力が上がらないために動揺してさらに制御棒を抜く内にコントロール不能の状態にしてしまったと考えられる。チェルノブイリ事故の場合は制限値を超えて手動で制御棒が抜かれていたという。そうなるとキセノンの毒効果が消え始めると同時に原子炉の中は急な核反応によって出力が爆発的に上がっていたことになる。
それに気付いた運転員が慌てて制御棒を燃料棒の中に入れた数秒後に偶然にも直下型の地震に見舞われて制御棒が折れ、ストップしてしまった。そのため、原子炉は暴走して一気に水蒸気爆発を起こしてしまったのである。これが、チェルノブイリ原発大事故の真相である。
私がこのような物理学の専門的な話を長々とするのは、このような原子物理学を学んでいる人達が原子炉の運転の現場にいないという現状が日本も同様なため、日本の原子炉はチェルノブイリ原子炉とは違って安全だという考え方で原発を運転していると、いずれ大事故を起こすぞという警告と注意のつもりで記述したものである。
つまり、チェルノブイリ原子炉事故も運転員の知識不足からくるミスと偶然に起こった直下型地震によって起きた事故とも言えるだろう。ここにチェルノブイリ事故から25年を経て、福島原発の大事故が起きて、やっと政府は浜岡原発の危険性に対して常識的な判断をやむを得なく下したのである。
(次号へ続く)